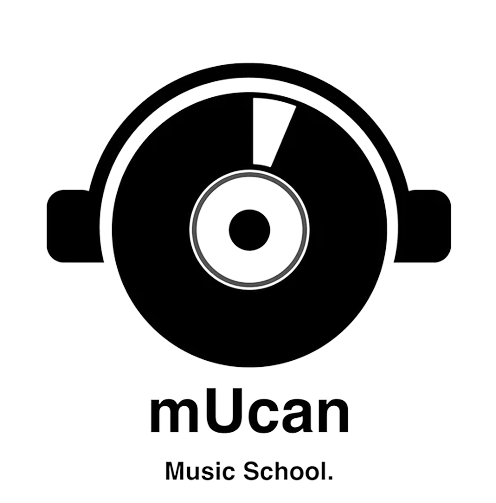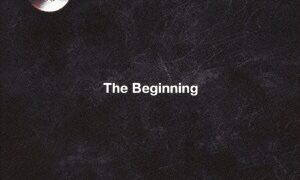【DTM講師が教える】作曲を始める前に知っておくべき7つの基礎知識

皆さん、こんにちは!ミューキャンミュージックミュージックスクールのDTM講師です!
このブログでは、
音楽制作の入り口である「作曲の基本」について、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います!
「いつか自分の作った曲でたくさんの人を感動させたい」
「趣味でDTMを始めたけれど、何から手を付ければいいかわからない」
もしあなたがそう思っているのであれば、
この記事はきっとお役に立てるはずです。
なぜなら、作曲は決して難しいものではなく、
いくつかの基本的な知識とステップを踏むことで、
誰でも音楽を生み出す喜びを体験できるからです!
この記事では、
【DTM講師が教える】作曲を始める前に知っておくべき7つの基礎知識として、
現役のDTM講師である私が、
音楽制作を始める上で非常に大切な7つのポイントを分かりやすく解説していきます。
これらの基礎をしっかりと身につけることで、あなたの音楽制作はよりスムーズに、そして豊かなものになるでしょう。
さあ、あなたもこのブログを通して、
素晴らしい作曲の世界への第一歩を踏み出してみませんか?
基礎知識1:音符と楽譜の基本 – 音楽の言葉を理解しよう

作曲の第一歩は、
音楽の基本的な言葉である「音符」と「楽譜」を理解することから始まります。
楽譜は、音の高さ(音程)や長さ(音価)、リズムなどを視覚的に表現するための地図のようなものです。
音符は、音の高さと長さを表す記号です。
丸や棒、旗の形によって、音の長さが異なります。
例えば、全音符は一番長く、二分音符、四分音符と短くなっていきます。
楽譜には、五線譜という5本の線が引かれたものが使われます。
この線や線と線の間に音符が書かれることで、音の高さを表します。
高い位置にある音符ほど高い音、低い位置にある音符ほど低い音になります。
また、音符だけではなく、休符という音を出さない記号も重要です。
休符にも音符と同様に長さがあり、音楽の流れにメリハリを与えます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、
基本的な音符と楽譜のルールを覚えることで、音楽の構造を理解し、
自分のアイデアを楽譜に書き起こしたり、
他の人の書いた楽譜を読んだりすることができるようになります。
焦らず、一つ一つの記号に慣れていきましょう。
基礎知識2:コードの仕組み – ハーモニーを生み出す魔法

メロディが音楽の「線」だとすれば、
「コード」は音楽に深みと彩りを与える「面」のようなものです。
複数の音が同時に響くことで生まれるハーモニーは、楽曲の雰囲気や感情を大きく左右します。
基本的なコードは、ルート音(根音)となる音から数えて、
特定の音程の音を重ねることで作られます。
最も基本的なコードは三和音と呼ばれ、
ルート音、ルート音から3度上の音、そして5度上の音の3つの音で構成されます。
例えば、
Cメジャーコードは「ド・ミ・ソ」
Aマイナーコードは「ラ・ド・ミ」といった具合です。
コードには、明るく響くメジャーコード、少し切なく響くマイナーコードの他に、
7thコードやsus4コードなど、さらに複雑で多彩な響きを持つものも存在します。
作曲においては、メロディに合うコードを選ぶことが非常に重要です。
適切なコード進行は、楽曲に流れと感情を与え、
聴く人の心に響く音楽を作り出すための鍵となります。
最初は基本的なコードから学び始め、
徐々に複雑なコードやコード進行に挑戦していくと良いでしょう!
基礎知識3:リズムと拍子 – 音楽の骨格を作ろう

どんなに美しいメロディやハーモニーも、
しっかりとした「リズム」と「拍子」がなければ、音楽として成り立ちません。
リズムは音の長さやタイミングのパターンであり、拍子は音楽の進行を一定の間隔で区切る役割を果たします。
拍子は、楽譜の冒頭に分数のような形で表示されます。
例えば、4/4拍子であれば、「四分音符を1拍として、4拍で1つのまとまり(小節)を作る」という意味になります。
3/4拍子や6/8拍子など、様々な拍子が存在し、それぞれに独特の雰囲気を持っています。
リズムは、音符や休符の長さを組み合わせることで生まれます。
同じメロディでも、リズムを変えるだけで全く異なる印象を与えることができます。
例えば、同じ音符の連続でも、アクセント(強調)をつける位置を変えるだけで、
躍動感が生まれたり、ゆったりとした雰囲気になったりします。
作曲においては、作りたい楽曲のイメージに合わせて、
適切な拍子を選び、魅力的なリズムを作り出すことが重要です。
色々なジャンルの音楽を聴き、どのようなリズムが使われているのかを分析してみるのも良い勉強になります。
基礎知識4:メロディの作り方 – 心に響く旋律を生み出すヒント

作曲の中心となる要素の一つが「メロディ」です。
心に残るメロディは、楽曲の印象を決定づけ、聴く人の感情を揺さぶる力を持っています。
魅力的なメロディを作るためのヒントはいくつかあります。
- 歌いやすいメロディを意識する: 自然で無理のない音の動きは、聴きやすく、覚えやすいメロディにつながります。
- リズムの変化をつける: 同じリズムの繰り返しだけでなく、音の長さに変化を持たせることで、メロディに表情が生まれます。
- 音程の跳躍を効果的に使う: 大きく音程が動く部分は、メロディのアクセントとなり、聴く人の注意を引きます。ただし、多用すると聴きづらくなるため、バランスが重要です。
- フレーズを意識する: メロディを意味のある短いまとまり(フレーズ)で構成することで、楽曲に流れと構成感が生まれます。
- コードとの関連性を考える: 作りたいコード進行に合うようにメロディを作ると、より自然で心地よい響きになります。
最初は既存の曲のメロディを分析したり、
楽器を使って自由に音を出してみたりするのも良い練習になります。
焦らず、色々なメロディ作りに挑戦してみましょう。
基礎知識5:構成とアレンジの基礎 – 楽曲を魅力的に組み立てる

素晴らしいメロディやコード進行ができたとしても、
それらをどのように配置し、どのような楽器で演奏させるか(アレンジ)によって、
楽曲の印象は大きく変わります。楽曲全体の設計図となる「構成」と、
それぞれのパートを彩る「アレンジ」は、作曲において非常に重要な要素です。
構成とは、
楽曲をどのようなセクション
(例えば、イントロ、Aメロ、Bメロ、サビ、間奏、アウトロなど)
で構成するかという設計のことです。
一般的なポップソングの構成だけでなく、
様々なジャンルの楽曲の構成を分析することで、
効果的な構成のパターンを学ぶことができます。
アレンジとは、
それぞれのセクションでどのような楽器を使用し、
どのような演奏をさせるかを決めることです。
例えば、メロディを歌で表現するのか、楽器で演奏するのか、
リズムセクションはドラムとベースにするのか、
シンセサイザーを使うのかなど、様々な選択肢があります。
作曲においては、作りたい楽曲のイメージを明確にし、
それに合った構成を考え、
各セクションの役割を意識しながらアレンジを加えていくことが大切です。
最初はシンプルな構成と楽器編成から始め、徐々に複雑な構成やアレンジに挑戦していくと良いでしょう!
おわりに:さあ、作曲を始めよう!ミューキャンでさらにステップアップ

ここまで、作曲を始める前に知っておくべき7つの基礎知識について解説してきました。
音符と楽譜、コード、リズムと拍子、メロディの作り方、そして構成とアレンジの基礎。
これらの知識は、あなたの音楽制作の土台となり、より自由で豊かな表現を可能にするでしょう。
作曲の世界は、無限の可能性を秘めています。
今回ご紹介した基礎をしっかりと身につけ、あなたの創造性を自由に羽ばたかせてください!
もしあなたが
「もっと深く作曲を学びたい」
「プロのDTM講師から直接指導を受けたい」
と感じたなら、
ぜひミューキャンミュージックミュージックスクールのDTMコースの無料体験レッスンをお試しください!
経験豊富な講師陣が、あなたの音楽制作の夢を全力でサポートさせていただきます!
あなたの音楽が、誰かの心を温め、感動させる日が来ることを心から願っています。
さあ、今日からあなたも作曲家への第一歩を踏み出しましょう!
投稿者プロフィール

-
弾けたらいいが弾けるに変わる
現役のプロミュージシャンからマンツーマンで学べるミュージックスクール
講師としての経験はもちろん、プロとしての演奏経験のある講師陣。
一人ひとりに合わせたカリキュラムを組み立て上達への近道へと導きます。
mUcanはオンライン、東京都、都内近郊、大阪にある個人レッスンの音楽教室です。
ギター、ベース、ドラム、DTMをはじめ様々な分野で活躍するインストラクターが
あなたの目標に対して、あなたのだけのカリキュラムを組み立てレクチャーしていきます。